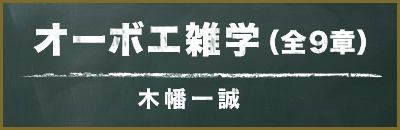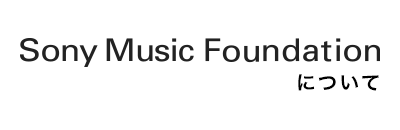オーボエ雑学
第1章
序にかえてーオーボエ、そのかけがえのない魅力の世界

まさに待望の開催ではありませんか。この2023年秋に予定されている、第13回 国際オーボエコンクール・東京のことです。
1985年の第1回から数えて、実に38年もの歴史を持つ国際オーボエコンクール。これまで3年に1回のペースで開催されていましたが、今回はコロナ禍による延期を挟んだことで、2018年以来のコンクールとなります。5年ぶりとなる開催を心待ちにしていたのが、世界中の若いオーボエ奏者たちだったことはいうまでもありません。歴代の入賞者のリストを見れば、コンセルトヘボウ管弦楽団をはじめとする世界のトップ・オーケストラの首席奏者など、綺羅星のごとき顔ぶれが並んでいます。新人が登竜門として目指す“ビッグ・タイトル”。そんな評価が既に確立されたと胸を張りたくなります。

このコンクールが発足したそもそものきっかけは、ソニー音楽財団の初代理事長の大賀典雄氏(1930-2011)が、若き日のベルリン留学時代に接したオーケストラの演奏で、特にオーボエの音から深い感銘を受けたことだと聞き及んでいます。「この楽器の真価を世に広めなければならない!」という大賀氏の使命感にも似た思いが、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者をつとめていたハンスイェルク・シェレンベルガー(第1回から審査委員をつとめ、第4回以降は審査委員長)との出会いも得て、素晴らしいイベントとして結実を見ました。
そのシェレンベルガーに代表されるオーケストラのトップ・プレーヤー。あるいはオーボエ界のレジェンドにも等しいハインツ・ホリガーを筆頭とするソリストたち。彼らが切り開いてきた道と到達した地平が、今日のオーボエ奏者の指針をなしています。その地平に立とうとする若者たちが、まるでオリンピックや世界選手権を目指すのと同じような姿勢で、日本の地を訪れている。……そんな思いを強くせずにはいられません。
そしてコンクールの開催を心待ちにしてきたのは、若いオーボエ奏者たちばかりではないでしょう。聴衆として彼らの演奏に耳を傾け、オーボエの魅力に目を開かされた、つまり大賀氏の思いを受けとめた方々も大勢いらっしゃるはず。
「葦笛」が喚起する豊かなイメージ
![]()
オーボエは辞書的に説明すれば「ダブルリード属の高音楽器」にあたります。葦を材料とするリードを加工し、それを唇にはさんで息を吹き込みますが、初心者にとっては安定した音を出すまでが一苦労。リードを自分で作る、あるいは細かな調整を施す技術もプロ・アマチュアを問わず不可欠で、時間と労力の点で相当な負担となります。そんな事情も手伝って、ギネスブックから「世界で一番演奏の難しい木管楽器」に認定されるという栄誉(?)まで獲得してしまいました。しかしそれを吹きこなしたときに生まれる音色の、何とまあ魅惑的なこと!
古代ギリシャの時代から存在する葦笛こそはオーボエという楽器の原点。そのイメージを現代に伝える、素朴で牧歌的で野を渡る風のような響きは、他の管楽器に求め難いものです。哀愁の情を誘い、郷愁の念を呼びさますのは大の得意技。ときにはエロティックな色気も発散し、一転してユーモラスにもふるまう。以上の形容にピッタリな作品の例を、今回のコンクールの課題曲に沿って列挙していきたいほどですが、それは別の機会に譲るとしましょう(予選と本選の演奏に耳を傾けていただければ話は早いですね!)。
心をじかに揺さぶる音の存在感
こうした表現力の幅にも増して印象に残るのは、演奏者の感情の動きを託した「歌心」を、じかに聴き手のハートまで運んでくるサウンド。その存在感と説得力の大きさです。筆者の個人的な、それもかなり以前の体験になりますが、予選から本選まで参加者すべての演奏に接した第8回コンクール(2006年)の記憶は今なお鮮烈です。長時間にわたり耳を傾けても感覚が麻痺するどころか、ずっと浸っていたいと思わせる何かが、オーボエの音には備わっている。それも吹き手が変わるごとに、気持ちがリフレッシュされて心が浮き立つような……。
その「何か」の秘密に迫るなどというのは、とても筆者の手に余ることですが、今後更新されていく“オーボエ雑学”のコーナーでは、この楽器を少しでも身近に感じられるような話題を取り上げながら、コンクールへの期待感をひときわ増していただけるページ作りにいそしみたいと思います。しばしお付き合い願えれば幸いです。
木幡一誠(Issay KOHATA)
音楽ライター。1987年より管楽器専門誌「パイパーズ」(2023年4月号で休刊)で取材・執筆にあたり、現在各種音楽媒体のインタビュー記事、CDやコンサートの曲目解説執筆およびレビュー、さらには翻訳と幅広く活動中。