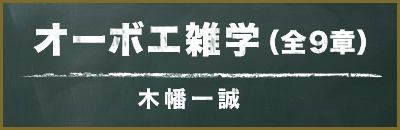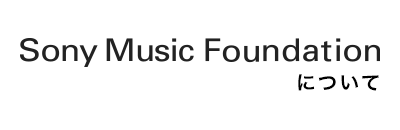オーボエ雑学
第9章
オーボエ素朴な疑問集2
Qどうしてオーケストラではオーボエに合わせてチューニングするの?

A.コンサートマスターの合図でオーボエ奏者がラ(A)の音を吹き、それに合わせて他の楽器が……。おなじみの風景です。遅くとも19世紀初頭には実践されており、その手間に不平を述べるオーボエ奏者の日記も文献に残されています。チューニングの音が聴きとりやすく、他の管楽器より安定した響きなので、オーボエが最良だという認識も古くから共有されていたのですね。
フルートやトランペットのような楽器は、管の抜き差し部分で長さを調整し、ピッチを上下させることが容易なのに、オーボエは構造上、それに相当するジョイント部分がほとんど存在しません。彼らのコンディションを優先して合わせるのが現実的な方策だったとも考えられます。
そんな経緯で、いわば儀式として定着したチューニング。楽団によって規準とするピッチを踏まえ(英語圏のオーケストラでA=440Hz、それ以外は443Hz前後が一般的)、チューニング・メーターという機械で確認しながらオーボエ奏者がラの音を吹き、みんなが合わせているというのが実際のところです。
Qオーボエの“ピリオド楽器”と“モダン楽器”って何?
A. 古典派やバロック時代、さらにはそれ以前の音楽を、作曲当時(=ピリオド)の楽器で演奏する試みが1970年代頃から活発化しました。これが現在では大きな潮流をなしています。当時の楽器といっても、特にオーボエの場合、博物館の所蔵品がそのまま使える例はほとんどなく、それを元に現代の工房がコピーしたものを用います。バッハの時代の作品なら、18世紀前半に作られたバロック・オーボエのコピー……というように。
そんな演奏行為から得られるものは? 作曲家が耳にしていたと思える音を再現する目的がまずひとつ。しかしそれにも増して重要なのは、当時の楽器の発音の特性や音域による響きの変化が、作品の書き方と密接に結びついているという考え方です。これはコンセルヴァトワール式のシステムで製作される“モダン楽器”が専門のオーボエ奏者と、ピリオド楽器の吹き手を比べた上の優劣ではなく、「何を道具として使いこなすか」というスタンスの問題としてとらえるべきでしょう。モダン楽器のオーボエ奏者が、古典派やバロック時代の曲に取り組む際、ピリオド楽器の奏法をどれだけ意識するかは各人各様。ただの表面的模倣では説得力がありません。それはコンクールでも問われる重要なポイントですね。
Qオーボエと他の管楽器によるアンサンブルにはどんなものがありますか。
A. 歴史的に見ていきます。
オトテール一族やフィリドール一族(第3章参照)の時代に盛んだったのが、主に野外での奏楽を目的とする“オーボエ・バンド”。サイズの大きなオーボエやバスーンも含むダブル・リード楽器属によるアンサンブルです。ヴェルサイユ宮殿における婚礼の儀の音楽なども、譜面として残されていたりします。
18世紀後半に、ウィーンを中心とするドイツ語圏で人気を得たのが「ハルモニームジーク」。オーボエ、クラリネット、ホルン、バスーン各2本が基本編成で、セレナードなどの娯楽音楽や、人気のあったオペラからの編曲版が主なレパートリー。モーツァルトやベートーヴェンも名作を残しています。
19世紀初頭に脚光を浴びたのがフルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、バスーンの「木管五重奏」。その後はいったん埋もれた存在になりますが、再びパリを中心とするヨーロッパ各地で復活を遂げるのが1870年代後半以降。オーボエでいえばコンセルヴァトワール式の普及期というのも象徴的な話です。そして20世紀に入ると、多彩な表現力や音色のバラエティも手伝い、管楽器による室内楽の代表的存在となります。
確立の時期において最も新しい形態が、オーボエ、クラリネット、バスーンによる「トリオ・ダンシュ」。フランス語で“葦の三重奏”を意味し、文字どおりリード楽器が1本ずつ。1927年に結成されたトリオ・ダンシュ・ド・パリの活動を契機に多くの新作が寄せられました。当然ながら響きの溶け合いに優れ、しかし小さな合奏体なので、各人の技術的負担は大きくもなります。
木幡一誠(Issay KOHATA)
音楽ライター。1987年より管楽器専門誌「パイパーズ」(2023年4月号で休刊)で取材・執筆にあたり、現在各種音楽媒体のインタビュー記事、CDやコンサートの曲目解説執筆およびレビュー、さらには翻訳と幅広く活動中。