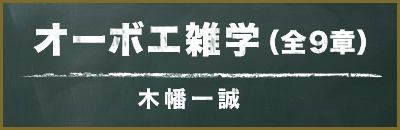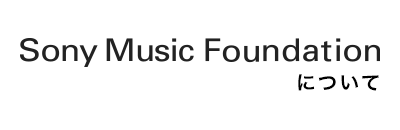オーボエ雑学
第6章
コンクール、ここが聴き所
音楽家としての成熟度か、原石の輝きか。
コロナ禍のもとで、国際コンクールも動画審査を導入することが一般的となりました。「第13回 国際オーボエコンクール・東京」でも第1次予選が動画審査で行なわれます。動画はコンクールのwebサイトで一般公開され、期間中は何度でも視聴が可能です。これはオーボエを手にした若い才能に接する上で、絶好の機会といえるものでしょう。
参加者は年齢的に10代の終わりから満30歳まで。音楽大学などで勉強中の人の比率が高いのは確かですが、既にオーケストラでプロとして活動している人や、他の国際コンクールで入賞歴がある人も珍しくはありません。そんな若者たちは当然ながら、音楽家としての成熟度が少しずつ異なります。第1次予選の動画の中で、まるでリサイタルのように堂々と振る舞う人もいたりするでしょう。あるいはそこまでの段階に達していなくとも、原石の輝きによって心を惹きつける人もいるはず。そしてどの演奏でも、オーボエという楽器に備わる“声”の魅力が、そのまま吹き手の人間性と結びつきながら耳へ届いてきます。
そんな第1次予選を楽しみながら「この人の“声”をもっと聴いてみたい!」と目を輝かせる出会いがあったとしたら、本当に素敵ではありませんか。そしてそれが第2次予選、さらに本選への期待へ結びつくとしたら……。
作品の質が高く「聴いて楽しめる」コンクール

第1次予選の課題曲は、バロック時代のテレマンと20世紀のヒンデミット。前者の「幻想曲」はもともと無伴奏フルート作品ですが、オーボエでも定番のレパートリーになっています。その「第11番」は技巧的に華やかなだけでなく、弦楽合奏のための協奏曲を1本のオーボエで吹くような場面が連続するのが特徴。そしてヒンデミットはどこか哲学的な色を帯び、1938年という作曲当時のヨーロッパに立ち込めていた、第二次大戦前夜の不安な空気も漂ってきたりします。まったく対照的な2曲を描き分けるという課題は、参加者にとってかなりシビアなものですね。
第2次予選は演奏時間が45〜55分の“ミニ・リサイタル”。生のステージで接する意味の大きいラウンドです。課題曲はA、B、Cのカテゴリーに分かれ、そこから何を選択し、どんな曲順で演奏するかも見逃せません。Aのバロック音楽で、ドイツの巨匠バッハと、ヴェルサイユ宮殿で活躍していたクープランのどちらを吹くかは参加者も大いに悩むところ。Bの課題曲は、リストやパガニーニにも通じる超絶技巧をちりばめた19世紀の作品、それぞれスタイルの異なる20世紀の作品、そして第11回のコンクールのために書かれた邦人作品、以上が合計7曲もあります。参加者が自分の音楽性をアピールする上での選択肢に幅を持たせたのですね。そしてCは協奏曲。オーボエ奏者にとって聖典に等しいモーツァルトと、チェコのマルティヌー、イギリスのヴォーン=ウィリアムズという20世紀の名作が並んでいます。第2次予選に駒を進めた俊秀たちが、どんなプログラムを組んでくれるか、今から興味をそそられずにはいられません。
音楽界の「動向」も感じとれる
このコンクールに足を運ぶたび、筆者は参加者のレベルの高さに驚嘆する一方、大きな時代の波まで感じたものです。仮に30年以上も前なら、たとえばドイツ語圏で学んだ奏者と、フランス語圏で学んだ奏者は、音色の傾向ひとつとっても明確な差異がありました。しかしその後は、特にヨーロッパの状況を見る限り、“EU化”という言葉に象徴されるスタイルの歩み寄りが生じています。こうした動きと共に、本当にいろいろな国で若いオーボエ奏者の層が厚みを増してきた事実も痛感しました。たとえばロシアやスペインといった国から次々と優秀な吹き手が現れては上位入賞し、第一線のオーケストラにポストを得ていく。そして日本も決して負けてはいない、等々……。音楽界の新たな動向をいち早く実感したという思いです。
そんなコンクールでも、最終的に問われるのは音楽そのもの。そしてプレイヤーとしての全人格的な魅力。まさにその点を浮き彫りにするのが本選の課題曲です。演奏者のすべてを映し出す鏡ともいえるモーツァルトの作品からは、古典派音楽の粋を極めたオーボエ四重奏曲。そしてそのモーツァルトの理想に立ち返った清朗な筆致の中に、ドイツ・ロマン派音楽の精髄をなす感情表現をこだまさせたリヒャルト・シュトラウスの協奏曲。この両作品を通じて、本選でくり広げられるドラマを堪能してみませんか。
木幡一誠(Issay KOHATA)
音楽ライター。1987年より管楽器専門誌「パイパーズ」(2023年4月号で休刊)で取材・執筆にあたり、現在各種音楽媒体のインタビュー記事、CDやコンサートの曲目解説執筆およびレビュー、さらには翻訳と幅広く活動中。