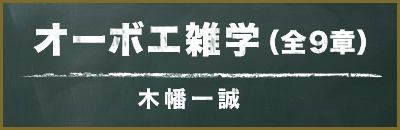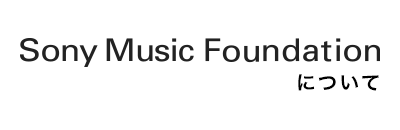オーボエ雑学
第7章
これだけは聴いておきたい! 名曲の中のオーボエ
胸を打つ名場面から野外での踊りまで
 貴方はオーボエ奏者です。「どんな音がする楽器なの?」と小さなお子さんにでも聞かれたら、一体何を吹きますか。チャルメラの真似なんて“ウケ狙い”はいけません(第2章もお読みください)。
貴方はオーボエ奏者です。「どんな音がする楽器なの?」と小さなお子さんにでも聞かれたら、一体何を吹きますか。チャルメラの真似なんて“ウケ狙い”はいけません(第2章もお読みください)。
「あ、それ聞いたことがある!」と目を輝かせてもらうなら、《白鳥の湖》の〈情景〉が順当なところかもしれません。チャイコフスキーの代表作にあたるバレエ音楽の第2幕冒頭で演奏される、おなじみのメロディーです。悪魔の呪いで白鳥に姿を変えてしまった娘たちの哀しい運命を象徴するかのごとく、バレエの舞台でもいろいろな場面に登場します。
こうした旋律でソロを受け持ち、オーケストラの中で圧倒的な存在感を示すのはオーボエの得意技。大作曲家たちもそれをよくわかっていました。たとえばベートーヴェンなら交響曲第3番《英雄》。第2楽章の葬送行進曲に宿された深い祈りの調べは胸を打たずにおきません。第4楽章のコーダを導く箇所に置かれた清朗な旋律には、音楽がそこで到達した地平を確かめるような内面的な充足感が漂います。同じベートーヴェンが交響曲第6番《田園》の第3楽章では、野外での楽しい踊りをリードする役目をオーボエに与えています。この楽器の牧歌的なキャラクターが全開になった名場面といってよいでしょう。
あるいはブラームスのヴァイオリン協奏曲の第2楽章。協奏曲の主役となるのはヴァイオリンのはずなのに、楽章の開始早々からえんえん2分間も、憧れに満ちた美しいテーマをオーボエが吹き連ねます。そこだけ聴いたらオーボエ協奏曲かと誤解すること必至ですね。
作曲家が人生を託した歌を奏でる
ときには色っぽくふるまうオーボエの姿にも接してみたくなります。そこで耳を傾けるとしたら、リヒャルト・シュトラウスの交響詩《ドン・ファン》。誘惑に負けた女性が主人公の腕に身をまかせ……というくだりで、この楽器に息長く濃密な表情のソロを配する呼吸は秀逸の一言。妖艶なまでに官能的な音色をオーボエから引き出す手腕は、オーケストラの魔術師と呼ばれたシュトラウスならではといってよいでしょう。その彼が第二次大戦の直後、創作活動も終わり近くの1945年に書き上げたオーボエ協奏曲は、透明感あふれる筆致の中に、ヨーロッパの貴族社会の最後の灯を見つめるがごときノスタルジーや愛惜の念が交錯していきます。モーツァルトの協奏曲と並んで、この楽器のレパートリーに輝かしくそびえる傑作のひとつです。
シュトラウスと同様に、しみじみと人生を振り返るような味わいを持つ作品としては、サン=サーンスが最晩年の1921年に完成させたオーボエ・ソナタも忘れることができません。同じフランスの作曲家で、お洒落なパリジャンという言葉を絵に描いたような作風で知られるプーランクも、世を去る前年の1962年に、遺作にあたるソナタを完成させました。辞世の歌を思わせる、深みのある名品です。
木幡一誠(Issay KOHATA)
音楽ライター。1987年より管楽器専門誌「パイパーズ」(2023年4月号で休刊)で取材・執筆にあたり、現在各種音楽媒体のインタビュー記事、CDやコンサートの曲目解説執筆およびレビュー、さらには翻訳と幅広く活動中。